



小説家
プロフィール
1975年愛知県蒲郡市生まれ、福岡県北九州市育ち。京都大学法学部卒業。 1999年、大学在学中に発表した『日蝕』により第120回芥川賞を当時最年少で受賞。 売上部数40万部を超える話題作に。 以降、数々の作品を世に発表し、2004年には、文化庁の「文化交流使」 として一年間、パリに滞在した。
美術、音楽にも造詣が深く、2015年マルタ・アルゲリッチ×広島交響楽団の「平和の夕べ」コンサートに朗読者として参加するなど、様々なアーティストとのコラボレーションも積極的に行っている。著書に、小説『葬送』、『滴り落ちる時計たちの波紋』、『決壊』、『ドーン』、『空白を満たしなさい』、『透明な迷宮』等、エッセイ・対談集に『私とは何か 「個人」から「分人」へ』、『「生命力」の行方~変わりゆく世界と分人主義』、『考える葦』、『「カッコいい」とは何か』等がある。2019年『マチネの終わりに』が映画化、累計60万部のロングセラーに。2021年8月に『ある男』の映画化も発表され、2022年に公開予定。2019年9月から2020年7月まで新聞連載していた最新作『本心』を、2021年5月に文藝春秋より単行本として刊行した。
ポートレート©ogata_photo

ここ5年10年ぐらい「未来」についてインタビューで聞かれる事がとても多かったんです。テクノロジーの進歩についてはなかなかわからないところはありますが、世界的には気候変動、日本でいうと少子高齢化。この二つは来るということが非常にはっきりしています。
僕には今年8歳と10歳になる子どもがいて、彼らが大人になった時にどのようにこの社会を生きていくのかということを、結構真剣に考えました。自分の世代の問題と自分の子どもの世代の問題を考えるうえで2040年代というのを念頭に置きまして、この気候変動と少子高齢化の二つの大きな条件を与えられている中、「テクノロジーの進歩」と「格差」を大きなテーマとしました。
特に格差に関しては、社会はそれが問題だということを百も承知ながら、日本に限らず世界的に、この格差を是正しようという力が非常に弱く、拡大の一途をたどっています。その問題を、小説を通じて考えたいというところから着想しました。
いつも書くときはあまり読者を絞らないようにはしていますけれど、未来の話ですからね。これからの日本とこの世界を生きていく人たちに読んでもらいたいと思って書きました。主人公も若いですから、若い読者には特に読んでもらいたいと思っています。
そして若い彼らに、未来のためにこれから何をやっていくべきなのかということを考えてもらいたいです。それから自分も含めて、これから高齢者になっていく世代には、若い人たちのために自分たちが一体何をしなければならないのかということを、小説を通じて一緒に考えてもらいたいとも思っています。読んでもらう対象によって読者に期待するところも、そういう意味では違っているとはいえると思います。
本心というのは、我々が対人関係の中でどうしても相手に期待するものですが、矛盾に満ちているし、動的なものです。昨日のその時点では心から真剣にそう思ったけれど、一晩考えてみたら変わった、そんなこともあります。では、昨日言っていたことは本心ではないかというと、そうともいえないと思うんです。どこにいても矛盾しない心、時間経過の中でも揺るぎのない心、それを確定することはなかなか難しい。それが本当のところ僕の考え方です。
ただ問題もあります。契約や社会システムは、本心から同意しているのであれば、それは是とすべき契約であり、是とすべき社会システムだというのが僕たちの社会の基本的な考え方だと思います。
たとえば、本心から同意してないのに契約を結ばされた場合、その契約は無効になります。逆にいえば本心から同意していれば問題ないはずですけれど、その本心は最初にいったように、非常に揺らぐものでもあります。そうなると本心というのは、一対一の個人間の心理的な問題以上に、社会システム全体の立脚点になっているんですよね。
人の心は揺らぐもので、人間関係の中ではそれを是とするにしても、それに根差しているはずの社会制度がぐらついてしまう、その問題を考えたかったんです。「本心」を主題にすることで、人間の心情的なレベルから社会システムの問題にまで話を展開させることができる。それが僕の思惑です。
僕はずっと、アイデンティティの問題を小説のテーマとして考えてきました。自分の中でそれは非常に複数的で一つに拘束されないということを、「分人」という概念を通じて書いてきました。
以前に小説『ドーン』で、人間のアイデンティティを最後に一つに収束させる要素として「顔」というのを取り上げました。
顔はどうしても変えようがないから、僕がいくらいろんな分人を持っていると言っても、この顔と外観がある限りは、平野啓一郎という一つのアイデンティティに括り付けられてしまうと思うんです。
意外と顔というのは原始的だけどアイデンティティの究極で、IDカード(免許証やパスポートなど)も顔写真が重要ですし、私たちが誰かを誰かとして認識するときには、やはり顔を見ているわけです。
ところが「アバター」は、その「顔」から人間を解放してくれる可能性があると思っています。実際SNSのアイコンは、すでに自分の顔ではないものを載せている人方が沢山います。バーチャルリアリティが今よりもっと具体的な世界性を備えていったときには、自分の好きな外観をまとうことができます。しかも脱着可能。これは私たちのアイデンティティに対する考え方を、非常に大きく変える可能性があると思います。
特にゲームの世界では、アバターは昔からあるごくありふれた概念だと思いますが、ゲームというフレームを越えて、日常生活の中で「自己以外の存在になりうる可能性」が開けていることに注目しました。『本心』にバーチャルリアリティ関連のものが多く登場するのもそれが理由です。
これは10年以上ずっと懸念していることで、特に東日本大震災も一つのきっかけだった気がします。それは共同体の構成メンバーをセレクトするという発想が、非常に強くなっているということです。
未曾有の危機でしたから、みんなで団結して頑張ろうというように、その時は言わざるを得なかったと思います。しかしそれをきっかけに、公共のためには私的なものは多少抑圧されてもしょうがない、そういう考え方が世の中にかなり強く出てきました。
一時の熱狂が過ぎた後に、次第に日本の財政危機などが語られていくと、金の使い道をめぐって、税金を何に使うべきなのかという発想が、共同体のメンバーをセレクトする発想と結びついてしまっているということに、強い危機感を覚えています。
救われるべきは品行方正な日本人だけであるという考え方が出現し、優生思想的な発想に繋がっていると思います。つまり社会の役に立っている人間だけが、共同体の構成員として尊重されるべきで、役に立ってない人間はどうでもいいんだという相模原事件(*)の犯人のような、非常におぞましい考えをしている人間が出てきました。
ひとりの人間の命を役に立つ、立たないとかって他人がジャッジするのはとんでもないことです。それは誰の命でもね。それに対する倫理的に間違っているという感覚と、心情的に許せないというこの二つのことが、自分の中にはずっとあるんです。
コロナを通じて色々な社会問題が嫌になるほど明らかになりましたから、それを真剣に考えていかなければならないことと認識して、その認識を多くの人と共有できたことは、一つ重要なことだったと思います。
気候変動は待ったなしで大変な問題ですけれど、ここ20年来、散々聞かされていたのに、いまいち現実的な問題として考えられなかったと思うんですよね。
今、世界中で森が燃えたり洪水が起きたりして、日本でも洪水被害が頻繁に起きていることを実感していますし、その中で「飛行機に乗るな」とか「肉を食べるな」とかいろいろなことを言われてきて、本当にそんなことできるのかなと懐疑的に思っていました。
しかしこのコロナで、世界中の人が飛行機に乗らないということが現実に起きました。不可能に思われていたことも、危機に直面する中で実現可能だということが、コロナを通して理解したことの一つだと思っています。「やればできるじゃん」みたいな。
基本的に、映画は監督と出演者の作品だと思っていますので、映像化にはあまり関わらないことにしています。彼らは専門家ですから、脚本に関しては少しだけ口を出したりはしますけれど、基本的には映画サイドの人たちにお任せしています。ですから僕にはほとんど苦悩はないです。しかし監督さんは大変だと思います。僕の長編小説は、デザイン的に工夫しながら、複数のレイヤーに整理して多くの情報を詰め込んでいますので、2時間映画に収めるのが大変なんですよ。
情報量に関しては、僕の小説には、ムーアの法則(*)みたいのものがありまして、昔は多くの情報を扱うにはそれなりの枚数が必要でしたけれど、年々小説家としての技術が向上して、すごく小さなところにたくさんの情報を圧縮して入れ込めるようになりました。それを2時間の映画にするのはかなり難しいと思います。
ですから、黒澤明が芥川龍之介の短編を映画にしたように、映画にする題材は、長編小説よりも短編小説くらいのほうがいいと思います。監督が自由に物語を膨らませた結果2時間になる、というほうが、詰めて削って何とか2時間に落とし込む、というよりも。長編小説を映画化しようとすると、映画監督をはじめとする映像関係のクリエイターは苦労されていると思います。
自分たちが生きていく中の「あったらいいな」を考え、それを形にしていくのが根本的なクリエイターの資質だと思います。今の生活に満足している人はクリエイターに向いていません。不幸だ、足りない、もっとこうであればいいのに、そういう不足の中からアイデアは生まれてきます。
物理的なものも、精神的なものも、思想的なもの、僕たち世代の人間が思いもつかないようなことを、今の若い人たちは考えていけると思います。すごく期待していますし、頑張ってほしいです。そして、そういう人たちが頑張っていけるような体制を、社会全体で作っていかなければいけません。でないと日本はどんどん寂しい冷たい国になってしまいます。
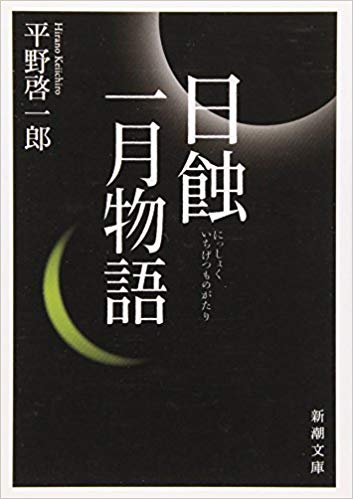
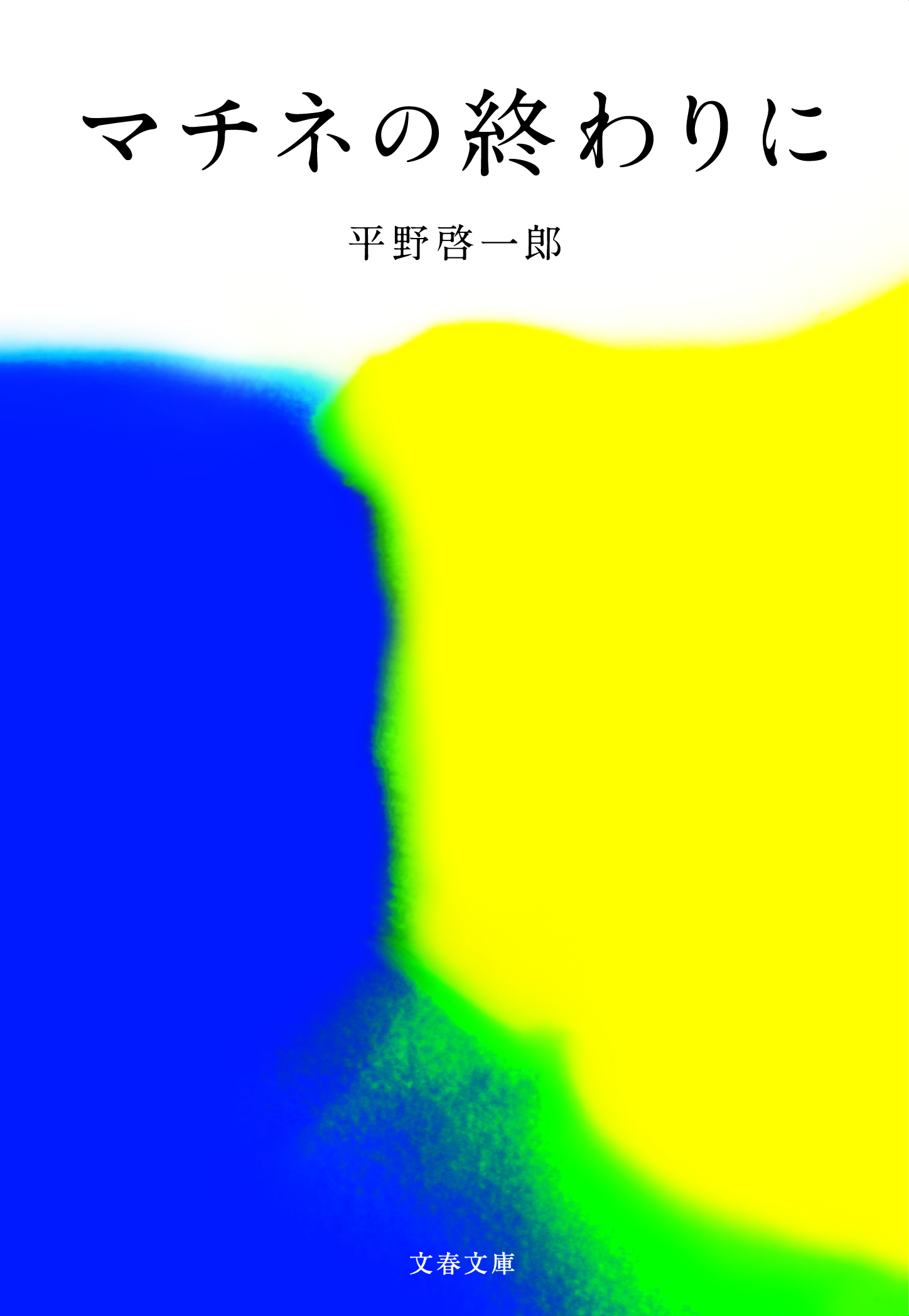

本文構成:河本ワダチ
取材担当:野水聖来/宮澤葵
取材場所:東京コミュニケーションアート専門学校(オンライン取材)
(取材日時:2021年 9月1日)